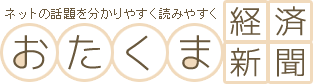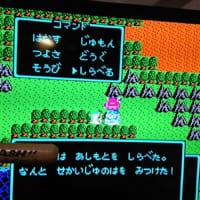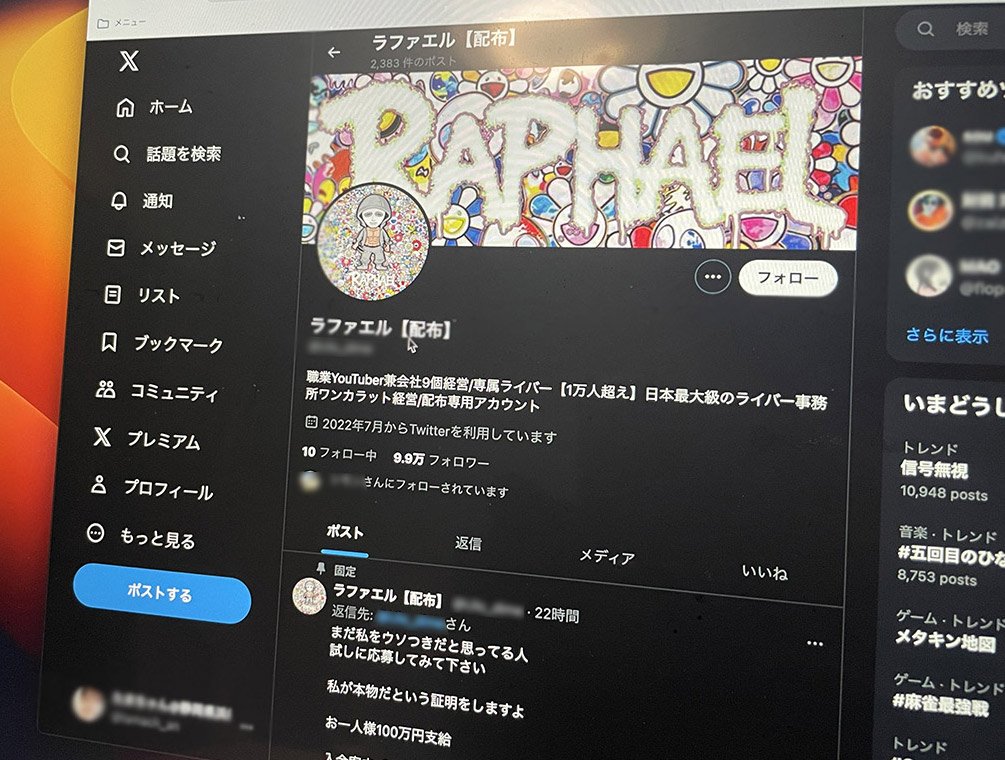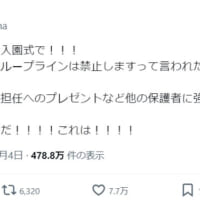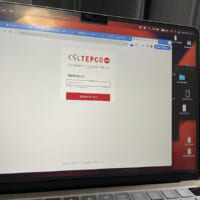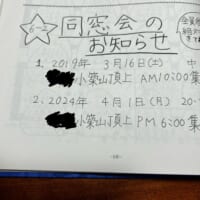故・梅本竜氏への想いと、バンド活動の中で築き上げてきた仲間たちとの絆を込め、約「20年ぶり」に作曲活動を再開して紡ぎ出したCDアルバム、『国本剛章WORKS~ひつじの丘~』が2012年の8月に発売された。
故・梅本竜氏への想いと、バンド活動の中で築き上げてきた仲間たちとの絆を込め、約「20年ぶり」に作曲活動を再開して紡ぎ出したCDアルバム、『国本剛章WORKS~ひつじの丘~』が2012年の8月に発売された。
ハドソンの名作ゲーム『チャレンジャー』などのセルフアレンジを含む全10曲が収録されている。
【関連:約20年ぶりに作曲活動を再開したゲームミュージシャン国本剛章氏インタビュー(後編)】
国本剛章氏に、学生時代とハドソン時代の話から近況、曲作りのルーツと、このCDのコンセプトを語ってもらった。ロングインタビューのため二部構成でお送りする。
――国本先生は、どのような学生でしたか?
音楽に関係することでいうと、小中学生の頃は、ピアノを習っていたんです。クラシックピアノを9年間。そこで基礎的なことは勉強して。中学校ぐらいからだんだんロックとか洋楽に興味を持ち始めて、ギターを弾き始めて、というよくある音楽経歴ですね。で、コードネームとか覚えて。
高校生の時は実は私、ずっとガリ勉くんだったんですよ。進学校に通ってて、大学受験をただひたすら目指したんですけど。志望の大学に入って。そこで軽音楽部に入ったんですね。そしたら人生が変わっちゃって。そのサークルがあまりにも面白くて授業に出なくなったんですよ(笑)
で、バンドばっかりやってて。あとはアルバイトをして稼いで、お金は全部楽器につぎこむという生活をしていて。それで、結局私は大学は6年間通って、しかも中退なんですよ……。で、その大学生の最後の方(中退する前に)で、ヤマハ(札幌の)でバイトをしていまして。そこで、「MSX」っていうコンピュータが出てきた時代で。ヤマハがそのMSXの中で動くシーケンサーのソフトを開発して発売したんですよ。で、それまではまともに動くシーケンサーがすごく高くて。100万円単位じゃないと買えなかったのが、ヤマハが開発したおかげで10万ぐらいで買えるようになったんです。それだと買えるじゃないですか。それで手が届くじゃないですか。「これは夢の機械が出てきた!」と思っていち早くそれを買って。色んな曲を打ち込んで楽しんでいたんですね。ヤマハのバイト先でもそれを仕事として生かしてほしいと。デモ演奏とかそういうのをやったり接客もしたりしてほしいと。ヤマハの店員は、その最新のソフトやPCは誰もできないから、それでやってくれっていわれて。趣味と実益を兼ねて自分の好き放題な打ち込みをやりながら、時々、接客をすると。それでお店からアルバイト代をもらうと。そんなことを大学生の時にやってましたね。まあざっと小中高大そんな感じですね。
――アルバイトでそういう実益を兼ねられるっていうのはラッキーですね。
その時はなんというか、友達からは非常にバカにされていたというか。要は「ちゃんと学校に行かずに、なんかそんなことやってて何になるんだろう」みたいなね……。親にも、もちろん心配されたし……。まあ、道をちょっと踏み外した大学時代ではあったっスかね。
――思春期はどのようなエンターテインメントを好まれていましたか。
思春期っていうのはだいたい中学高校ですかね。私が中学のときは、やっぱり、TVですよね。で、『太陽にほえろ』という番組があったのですがご存知ですか? あれの番組の中で音楽がかかるんですけど。よくいわれる「劇伴」っていうやつですね。場面によって色んな曲がかかるじゃないですか。犯人を追いかけてる場面、激しい音楽だったりだったとか、ちょっとサスペンスっぽい音楽、殺人の現場とか。それから、最後の格闘シーンの勇敢な音楽とかね。あとはやっぱり、犯人が捕まって反省して悲しい場面の音楽とか。そういうのをこう。場面と音楽が合ってるのを聴くのが大好きで。これはいい音楽だと。で、絵音楽って名作がいっぱいあるんですけど。あの、オーケストラとかも、もちろんいいんですけど。その『太陽にほえろ』は、井上バンドっていうロックバンドがやってたんですよ。それでその、いわゆる、ドラム、ベース、ギター、キーボートっていう編成で。それがその、中学校ぐらいの時は、シビレてたんです。カッコイイと思って。
それを中学校の時は、ラジカセをTVの前に置いて、ライン録音とかできないから。TVのスピーカーに近づけて。マイクで録って。家族の色んな団らんの声とかも入っちゃうんですよね(笑)それを後から何十回も聴きながら曲を覚えて。それがもう楽しみでね。それが一番ですね。それで、まだステレオとか持ってなかったんで。本当にラジカセ一台しか持っていなかったんですよ。スピーカーもモノラルでね。本当にちゃっちい音しかしないんですよ。それが唯一の自分の音楽を聴く環境であってね。ひたすらそれを聴いていたと。ステレオを持っている友達がうらやましかったですけどね……。
例えば、子どもの時に、やっぱり親が厳しくて、ゲームをさせてくれなかったけど、友達の家に行ってひたすら遊んだとかね。あと、ソフトが高かったじゃないですか? だからね、ほしいのは買えなくて。例えば、誕生日とクリスマスに一本ずつぐらいしか買ってくれないから。ちょっとお金持ちの友人の家に行くと、ソフトがいっぱいあって。そこに行ってひたすら遊んだと。という話を聞くと非常に共感するんですね。その……意外と与えられてない環境の方が、なんか、より貪欲にその、楽しめるっていう。そんな気がしますね。なんでも裕福に買い与えるとなんかこう……本当の面白さが解からないからねえ。
(国本)――川上さんはどうだったんですか?
僕はそうですね。ファミコンのカセットはお正月とクリスマスぐらいに買ってもらえればよい方で。たまに、クリスマスに「コロコロコミック」一冊とか(笑)
(国本)――じゃあ、その「コロコロコミック」を暗記するほど読むわけでしょう?
そうですね。同じページを何度も何度も読んで。今でも、その話の内容を覚えてますね……。
――国本先生はクラシックに興味があるかと思ったのですが、意外と「太陽にほえろ」とか、ロックとかだったんですね。
クラシックはねえ……。あの、小学校、中学校、一応、ピアノをやってたんで。その基礎はあるんですよね。だけど、大好きではなかったですね……。もちろん、好きな曲もあるけど。なんか退屈だと思った時もあって。で、やっぱりそうですね。そこから高校、大学ずっと通じてもクラシックはなんかたまには聴いてたけど、熱中はしなかったですね。
――いつからベースは始められたんですか?
ベースは大学生からですね。その時に、軽音楽部に入ったと言ってたじゃないですか。最初はキーボードでやってたんですよ。で、ところがなんか大学の途中の3年生ぐらいから。当時ねえ、パンクとかニューウェーブとかバンド名でいったら、セックスピストルズとか。あとね、日本でいったら、ヒカシューとかARBとか。あと私が好きだったのは、戸川純とか。矢野顕子とかちょっとトンガってたんですよね。その頃の日本の、ちょっとやっぱり毒を含んだようなメッセージ性のある曲が好きだったので。
それで、自分で歌いたくなったんです。そしたら、なんかね、キーボードで歌う。例えばパンク調の歌を歌ってもカッコがつかないんですよ(笑)
やっぱ、なんかこうやって歌わないとダメだなと思って。フロントで歌うためにちょっとベースをやり始めたんですね。だからなんかそういう、今聴いたら恥ずかしいような曲をね、歌っていましたよ。若気の至りですね。
――イカ天にもご出演されていたそうですが。
それは26歳ぐらいだったかな。その前に大学の辞めるきっかけになったのは、そこであのハドソンの仕事が始まったわけですよ。で、あの、そういう何本か仕事をして。これ、「俺これでなんか生活できるんじゃね」って思って。で、大学を辞めて。辞めて、そのファミコンの仕事をするかたわら、バンドもやってたんですよ。で、そのバンドの方でどっちもがんばろうと思って。札幌に住んでたんですけど。26歳の時に、バンドのメンバーと一緒に東京に出てきたんです。で、出てきて、そのイカ天をちょうどやってたんで、応募して、当時は応募したら出れたんですよ。
――すごいですね。イカ天といえばバンドブームで、出ることがまず難関だったわけですよね。
今でもイカ天出身のバンドいっぱいありますよね。
――ユニコーンとかそうですね(実際には、FLYING KIDS、JITTERIN’JINN、BEGIN、たま、カブキロックス、人間椅子など)
自分たちは出られたんですけど、一勝も勝ち抜けず、一回戦で落ちたんですけどね。
――その時はどういう曲をやられたんですか?
その時はオリジナル曲でやったんですけど。あの、「プログレ」ってわかります? プログレッシヴ・ロック。そういうジャンルがあって。まあ、えとバンド名でいうと、イエスとかキングクリムゾンとか。そういうバンドがあって。ちょっと小難しいことやるんですよ。変拍子とかって解かります? 4拍子とか3拍子じゃなくて、5拍子とか7拍子とか。ちょっとだから、ノれないような小難しいことをね。やったりとかして。でもなんだろう。そのまあ、あのメッセージ的な曲を歌ってる頃よりはまだマシ(笑)
というか、音楽的なものをちょっと突き詰めようと思って。そういうね、実験的な曲をやったりとかしてました。
――その時の貴重な映像って残ってるんですか?
一応、ビデオに撮ってはあるんですけど。画質が悪くなっちゃってダメですね。
――ご自身の曲作りのルーツのようなものはありますか?
作曲で影響を受けたと思う人が、ざっくり言って3人いて。一人が、「太陽にほえろ」の曲を作った大野克夫さん。井上バンドのキーボードをやってたのね。で、その人と、あとは、冨田勲さんってご存知ですか? シンセサイザーの多重録音で世界的に有名な人なんですけど。で、あと、『ウルトラセブン』ご存知ですか? あれの曲を作った冬木透さんっていう。その『ウルトラセブン』っていうのご覧になったことありますか? あれね、子ども向けと思いきや実は結構、大人も楽しめるようなストーリィにもなっていて。音楽も、今聴いても遜色がない十分聴けるような本当に大人向けなんですよ。
それで、それを子どもの時に聴いて、不思議な気持ちがして。あの、再放送で何度もされたので、小学校の高学年とかもうずっと観てて。大分それは影響を受けましたね。その3人が特に影響を受けた人です。やっぱりどれにしても結局、映像があったりして、それに付いてる音楽っていうのが好きで。だからあの、ゲームの音楽をやらないか? って言われた時に、すごく嬉しかったんですよ。やっぱり、自分もゲームが好きだったんスよ。自分はゲームでいったらね。『マッピー』とかあれがもう、喫茶店とかのテーブル筐体であった時ってご存知ですか? で、あの当時のナムコの曲ってすごく良くて。もう、夢中になって結構お金使ってやってて。やっぱああいう感じで自分も役に立ちたいなと思って。絵と音楽が一緒というのが好きですね。
――国本先生の曲って、絵(シーン)にとても合ってますね。
そういっていただけると嬉しいですね。
――先ほど少し言及されていましたが、国本先生の場合は、商業でお仕事をされるようになったきっかけは何でしょうか?
さっきいってた大学生の頃に、ヤマハという楽器のお店でバイトしてて。そのMSXっていうコンピューターが出てきて。それを自動演奏の自分で打ち込んで。お店でデモ演奏とかやってたわけですよ。そしたらそこに、たまたま札幌で、そんな狭い都市というか、楽器屋だって有名なところはあんまりないんで。ハドソンの音楽担当者が、たまたま来たわけですよ。たまたまっていうか、ハドソンは、当時、ファミコン作り始めて間がない頃なんですけど。プログラマーは優秀な人がいっぱいいたけど。音楽を作れる人がいなかったんで。作曲家を探してたんですよね。で、楽器屋に担当者の人が来て。そしたらたまたま自分の作ったデモ演奏が流れてて。そんで、耳を止めてというか。で、これ作ったのあなたですか? っていわれて。「ああ、そうです」っていったら、なんか今度、会社に来てもらえませんか? っていわれて。それがきっかけなんですよ。
それで行ったら、1作目が『チャレンジャー』なんですけど。それを作っている最中で。で、画面がまあ……7、8割出来ているような感じですよね。それを観せてもらって。まだ音は付いていないわけですよ。「これに曲をつけてくれませんか?」というお試しみたいな感じのね。そのヤマハのシーケンサーで打ち込んで。それを持って行ったら。それで採用になったっていう話ですね。
――素晴らしい曲だったんですね。
最初は、クラシックのね。『チャレンジャー』っていうのは、シューベルトの「軍隊行進曲」っていうのをアレンジしてるんですけど。まあとりあえず、みんなが知っている曲で、あのゲームはやっぱり小学生が主に遊ぶだろうと思ってたので。自分が小学校の3、4年の時に「軍隊行進曲」を音楽の時間に聴いて。結構好きだったんですよ。たて笛とかで吹いて学校から帰ってきた記憶があるんで。多分、今でも小学生はその曲が好きだろうと思って。確かそれを使ったと思うんですよ。そしたら採用になって。そっからですね。ヤマハのMSXっていうのがちょうど出てきて。私が札幌にたまたま住んでいて。で、その、ハドソンの本社が札幌だったんで。その偶然の一致ですよね。だからそこで出会えたっていうだけであって。ハドソンが札幌に無かったら出会えなかったねえ(笑)
――色々な偶然が重なって。そして、実力が認められたと。
一応、そんな感じですね。
後編へ続く――。
【プロフィール】
国本 剛章(くにもと たけあき):『チャレンジャー』『迷宮組曲』『スターソルジャー』『忍者ハットリくん』など、今も幅広い世代から愛されているファミコンのゲームミュージックを世に送り出してきた。札幌出身で、大学時代はヤマハでアルバイトをしていた。1990年に『三宅裕司のいかすバンド天国』にバンド出演している。
【リリース情報】
アルバム
『国本剛章WORKS~ひつじの丘~』
販売日:2012/8/3
品番:SRIN-1097
定価:2,100円
【オフィシャルサイト】
「キノコさんの休憩室」
https://sites.google.com/site/kinoko3qkc2/
【販売】
「Sweeprecord」
http://sweeprecord.com/
【ツイッター】
https://twitter.com/kinokowakame
(インタビュー:川上竜之介)