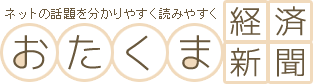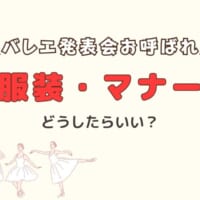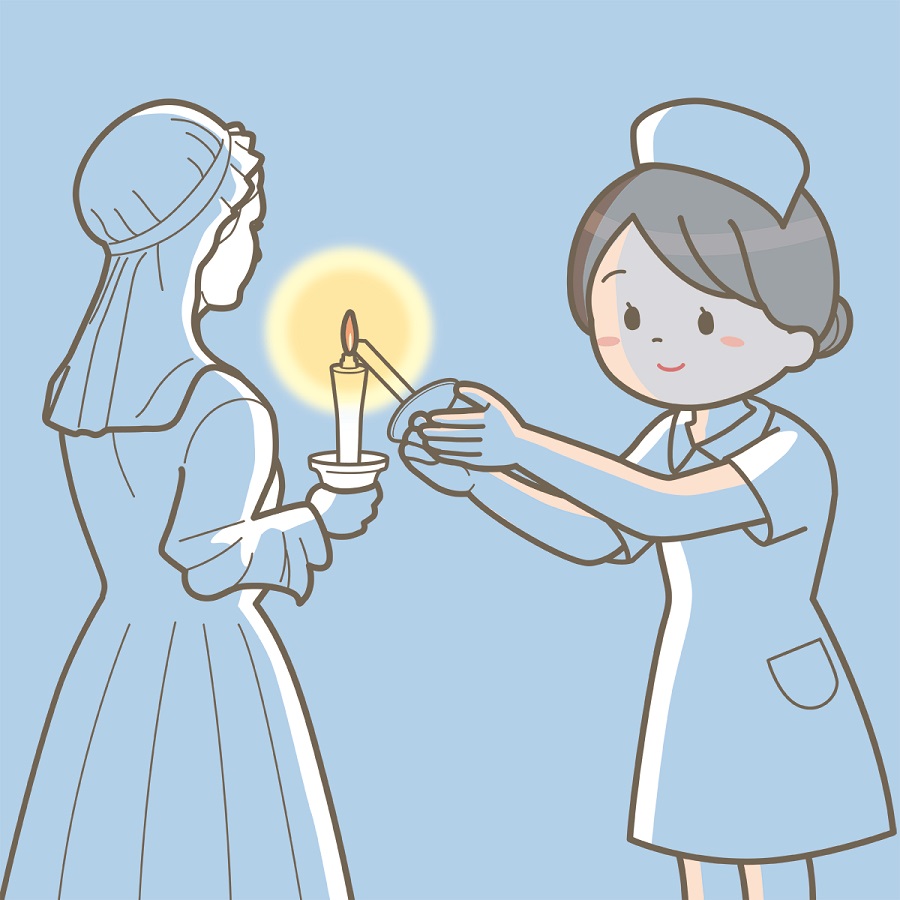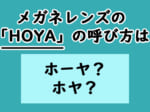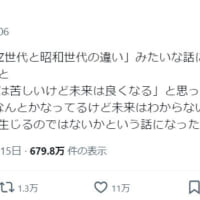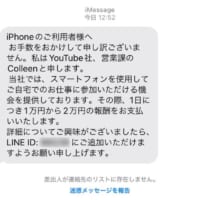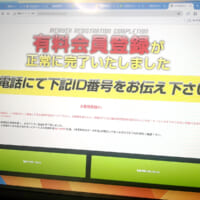世の中、実に多くの職種がある中で、人の命に直接向き合う仕事の一つが看護の仕事。読者の皆さんも、医療ドラマや看護のドラマで何となく「看護師ってこんな雰囲気なのかな……」って感じるところもあると思います。今回は看護の日という事で、筆者が向き合ってきた命の一つ一つを振り返ってみます。
■ 「人のシモの世話なんて」が入院して見え方が変わったうちの父
筆者こと私が看護師を目指したのは、自分でも物心がついていない時。2~3歳のころに見ていたアニメの主人公に憧れて以来、ずっとなりたいと言ってきたのです。小学校の作文などで「将来の夢」をテーマに書く事になった時は、さすがに「アニメに影響されて」と書くのが恥ずかしかった記憶があります。ただ、3歳のころに一度、1週間ほど入院していた事があったので、それをきっかけにとお茶を濁して書いたような……。
アニメの主人公と、入院していた頃の体験がクロスオーバーしていたのかもしれません。しかし、父は私が中学の時に「真面目に将来の進路は看護師を目指す」と言った時「そんな人のシモの世話をする仕事なんて」という言葉を言い放ったことがありました。正直、その言葉には声が出ないほどにショックを受け、以来父親に嫌悪感を抱き、一言も話さなくなりました。
言霊なのでしょうか?父はそれからしばらくして、命に別方はないが手術して摘出した方がよい体内のできものを取るために入院しました。父が入院するまで一切口を利きたくなかった私。母に連れられて一度だけ病室を訪れたことがありましたけど、何となくぎくしゃくしていました。
無事に退院してから、「看護の仕事って、すごいんだな」と父が一言。入院という体験によって、偏見が崩れた様でした。それから、父も私の進路について応援してくれるように。実体験ほどものの見方を変えるものはないのだなあ、と思った出来事でした。
■ 実習先で泣き崩れた私
看護師になるために必ず通らないといけない、看護実習。指導看護師が怖い人に当たるか、優しくてもメリハリ付けた教え方をしてくれるかで天国か地獄が決まる実習でした。当時は、ほぼ地獄。でも患者さんとのコミュニケーションはおおむね良好にできていました。
看護資格のない実習生ができる事と言えば、洗髪や足浴、清拭など患者さんの清潔を保つケアや、コミュニケーションから患者さんがどのようなケアを必要としているか、退院後どうしたいかを上手く引き出し、学生なりに必要なケアを一日の実習に組み込むレポートを作成し、実習先の指導者さんに提出、実施する事。なかなかベッドから起きない患者さんを促してお散歩を一緒にするのも、ケアの一つでした。
毎日必死にレポートを書いては、赤ペンでみっちり突っ込まれる日々。「このケアをやる根拠は?優先順位は?」じつに厳しい指導を受けながらも、受け持ち患者さんに逆に癒やされたりといった事も。
外科の実習の時、私は大腸がんからストーマを造設する60代男性患者・Aさんの受け持ちになりました。最初はストーマの造設に後ろ向きだったAさんが、一大決心をして手術を行い、無事に手術が成功した時、「これで(ストーマに)慣れていけばいいんだな」というAさんの言葉に、前向きに受け入れてこれからの人生を楽しんでもらえると、私まで嬉しくなった事を今でもはっきりと覚えています。
実習が進むにつれ、Aさんに少しずつ笑顔が戻りかけた時、実習期間は終わってしまいました。Aさんが私との対話を楽しみにしてくださったのも、その後の自分の実習の励みになりました。
他の科の実習に入った私はその後、ストーマを作った後にAさんが順調に回復していっていると思っていました。……が、「梓川さん(筆者)が受け持ってた患者さん、調子悪そうだから顔を出してあげて」。そう聞かされた週明け。私は病室に行く事もなく外科病棟で泣き崩れてしまっていました。笑顔でこれから頑張ろうって言っていたはずなのに、どうして……。
実習が終わった後、Aさんはだんだん元気をなくしていったと聞かされました。そして、急変。帰らぬ人に。私は、心底悲しく、力のなさを思い知りました。いろんな思いがあふれて詰め所でつい泣き崩れてしまった時に、私の指導に直接当たっていなかった看護師からの言葉は今でも心に残っています。
「急変は突然来ることもあるし、これは誰のせいでもない。でも、学生さんだからと言ってここで泣いているのはダメ。死に対して慣れちゃいけないけど、泣き崩れるのはやめよう」
そう言われた私は、何とか気持ちを落ち着かせて当時住んでいた学生寮へ戻ったのでした。無力感、自分が役には立たないのではと思う恐怖、でも私はずっと看護の道を歩んできた……。いろんな気持ちがぐちゃぐちゃでした。
■ もしかして、患者さんは……
無事に国家試験もパスし、看護師になって数年した頃、私は総合病院の呼吸器病棟にいました。当時中途で入職した病院は、お世辞にもきれいとは言い難い、ふるーい感じ。そこでは、数名の患者さんが人工呼吸器を装着していました。
高度成長期時代、大気汚染がひどい地域だった事もあり、公害で肺がおかされてしまったのです。肺の中にはブドウの房のような、肺胞という小さな空気の交換を行う袋状の物が肺の中におさまっており、肺胞が膨らんだりしぼんだりする事で、酸素を取り入れ、二酸化炭素を排出する機能を担っています。しかし、粉塵などが肺胞の中にまで悪さをしてしまうと、肺胞が膨らまなくなってしまうのです。膨らむはずの風船が、ガチガチに固まってしまう様な感じといったところ。
症状が軽い人は、在宅で酸素を補って生活ができますが、自発呼吸が上手く行えない場合、人工呼吸器をつけます。首元に穴をあけ、気道から気管チューブを直接つないで、人工的に酸素を混ぜた空気を送り込むのです。
私が転入してしばらくして、病院の引っ越しが決まりました。紙カルテは電子カルテに切り替えられ、病棟もきれいに新しく、明るくなりました。人工呼吸器の患者さんたちも、救急車の力を借りて無事に全員事故もなく、引っ越しが完了。
当時人工呼吸器を付けていた患者さんは、何かしらの介助があれば病室内で生活できたり、肺機能以外はほとんど問題なかった人も。口パクからかろうじて漏れる息や、筆談でコミュニケーションを取れる人がほとんどでした。
そのうちの一人の女性患者・Bさん、といっても、結構な高齢でしたが。新しい病室に入った時、「とっても明るくていいお部屋」ととってもニコニコしていたのち、何かしら数珠を手にかけて笑顔のまま拝んでいました。先立たれた旦那さんに報告しているのかな、と思ったのですが……。
私が出勤したのは、その翌々日でした。病室一覧のボードに何か足りない違和感。Bさんの名前がない!「Bさん、どうしたの?」と前日も勤務だった同僚に聞くと、何と、その翌夕に息を引き取ったというではないですか。引っ越し後にはご家族も病室を訪れ、「明るくなっていいところに入れたね~」などとご家族もニコニコとお話をしていて、全く急変する様子もなかったのです。
明け方、呼吸器のアラームが鳴り止まない事に気が付いた夜勤者が大急ぎで当直医を呼んだ時には、もう心肺が止まっていました。その時のお顔はとても安らかで、気持ちよく寝ているみたいだったと聞かされました。
生前、引っ越しの話をした時には、「ちょっと不安だけど、楽しみ」と言っていたのをふと思い出し……これは、都合の良い解釈なのかもしれません。新しい病室に来れて、思い残す事がないとご家族に話していて「またまた~。ここでもっと新しい病院生活を、見晴らしの良くなった窓の眺めを楽しもうよ」とご家族が返していたそうですが……。高齢になって、本当に思い残す事がなくなると、人間、自分で人生を締めくくる人もいる、と感じたのでした。
この人工呼吸器のBさんに限らず、夜中にお茶を飲みながら一人何かぶつぶつとつぶやいていた患者Cさん、独り言が終わったと思ったらこと切れていた、という例も起こっていました。その高齢男性のCさんは一時はひどいせん妄もあり、急激な経過をたどっていました。詰め所からも良く見える重症用個室に入ってもらって2日位経った頃でしょうか。容体は落ち着いているようにみえました。その晩遅く、Cさんはベッドから体を起こし、一人何やらつぶやいていたのです。もしかしたら人生の全てを振り返って、ひとり納得して旅立っていったのでは……。
病棟での看取りのいまわの際、ひどい認知症の状態から突然、正気に戻って、それまで忘れていた家族の名前を呼んだり、先立たれたパートナーに向かって「今行くからね」と天井の斜め上を見上げてそのまますうっと眠りに入るように人生の幕を閉じたり……。何度か見てきた光景は、十数年経ってもやはり心に残っています。泣きそうになって泣かなくなっても、慣れるなんて事なんか全然なくって、もう二度と目も開けてもらえなくても、お返事が聞こえてこなくても、最後に体を拭いて、新しい寝間着に着替えてもらって、と処置をしている間も、ずっと、「○○さん、次はこちらのお袖に手を通しますね」などと話しかけて。処置には慣れても、さっきまで温かかった体がこれからだんだん冷たくなっていく事は、やはりどうしても慣れることはできませんでした。いつも通り声をかけながら、いつも通り清潔のお手伝いをして……。
一方で、90歳を過ぎてもう終末期であることがカルテからも本人の状態から見てもわかる状態ったDさん。深夜勤務者に申し送りをしようと準備していたところ、数分続いたら確実に心臓が止まってしまう心電図の波形に。当直医を呼びつつ、普段は滅多に出る事のない除細動器を他の階から借りてきて、電気ショックを何度か与えている間に家族を呼んで……という事も経験しました。入院してきてからのDさんは既に意思表示もできない状態。それでもできる限り生きていて欲しいというご家族の意向で、蘇生しようと繰り返したのです。内心、小さくなった体が電気ショックで跳ね上がるたびに、あまりにも辛くて「お願いもう終ろう?」と思ってしまった事も。
結局、心電図の波形は戻る事はありませんでした。あらかじめご家族にも、いつ何があってもおかしくありませんと伝えておいたからか、その後トラブルになる事もなくお見送りをしたのでした。
■ 看取り、自然に逆らえない命と、「どう生きるか」
黒い特別車を、線香のにおいが漂う地下の専用出口から深々と一礼をしながら見送った……。看護師として病棟に勤務していると、何度かそんな経験をする事があります。
そのたびに「この病院で最期を迎えた事、どう思ってくださっているんだろう」と考えてしまう事があります。生きている以上、必ずどこかでその命は終わります。人生に正解はなく、生い立ちが人を歪めたり、元からの持病、特性、その他諸々の事柄が一人一人の人生に絡み合って日向となり陰となり、やがて終わりに向かいます。
後悔のない生き方なんて、全くない人なんていないはず。私も、後悔の連続でした。重大な選択肢を間違えたと思った事もあります。
でも、そんな時に入院した先の看護師さんが話を聞いてくれたり、「だから今こういう事に気が付いているんじゃないの」と励ましてくれたり……私は、できていただろうか?看護師として、誰かの目や耳や杖の代わりに、少しはなることができただろうか?
今なおもってまだ答えは出ません。でも、看護師としてできる事、それは対象となる人をよく観察し、どういう思いでいるか感情を分かち合い、必要なケアを提供する事なのでは、と一個人として思います。人生の一番最期に、「色々あったけど、あの人に出会えてよかった、総じて悪くない人生だった」と思えるように、ケアができる存在。それも看護師の役割のひとつなのかな、と思います……。
良かった・良くなかったの尺度は人によって違うでしょう。でも、「終わり良ければ総て良し」が実現できるためには普段からも自分の最期について、家族と話し合っておく事が必要かもしれません。その時に迷ったら、かかりつけの主治医や看護師に相談してみてください。患者さんを診察して、看護している医師や看護師、そして高齢者で介護を受けていてケアマネージャーがいればそちらにも。「生きて終わりを迎える」事について、全力で相談に乗りますから。
(梓川みいな/正看護師22年目)