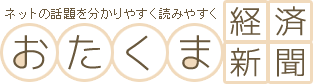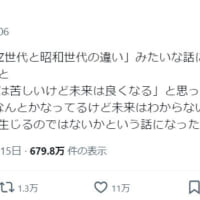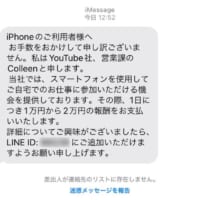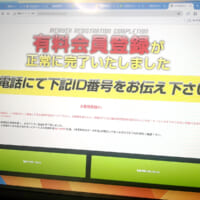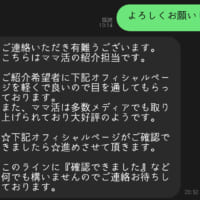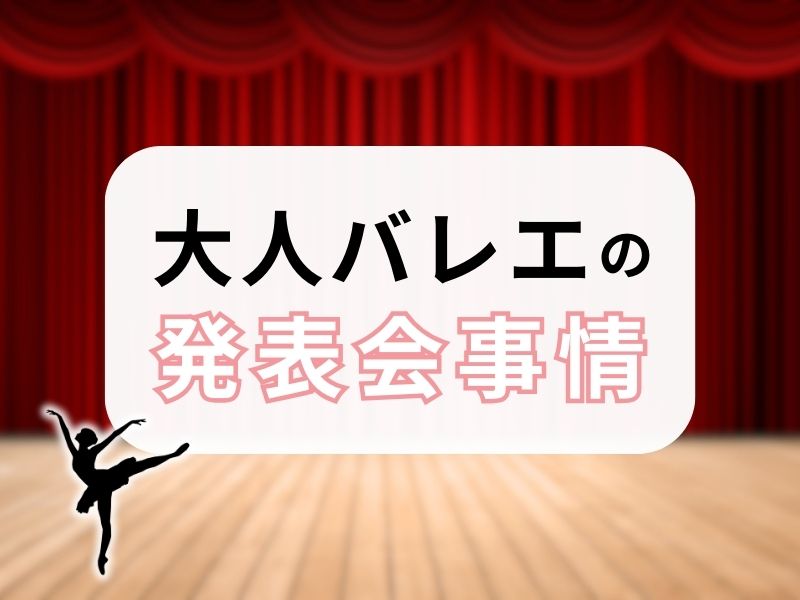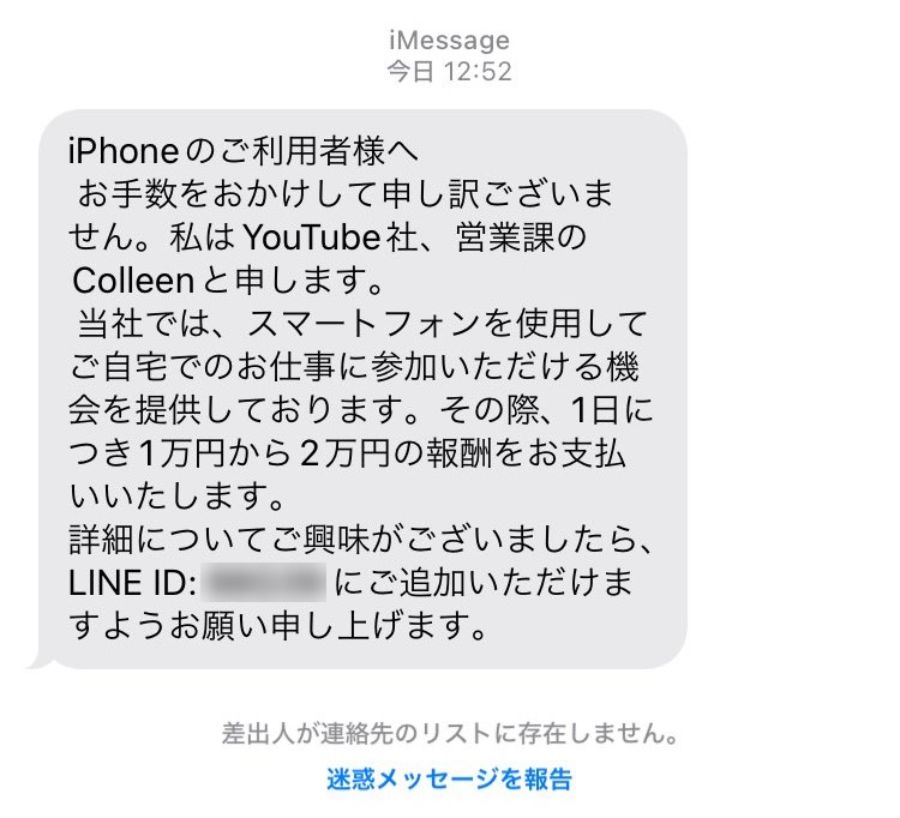認知症になると、出来ていたことができなくなり、覚えていたことが分からなくなる、というイメージが大きいと思います。しかし、好きだったものは心のどこかで生きています。そんな元ロックギタリストの高齢男性のお話に、グッと来ている人が続出しています。
「『認知症で家族がもう何もできないと思い込んでた70代のじーちゃん』が元ロックギタリストで。デイに行きたくないっていうから『スタジオ』に行ったら『Deep Purpleのハイウェイスター』を一曲バキバキに弾ききった最高にクールな現場からは以上です」と、とある日のデイサービスでの出来事をツイッターに投稿したのは、介護教員や研修講師、まちづくりデザインNPOの運営などを行っている軍司大輔さん。
この男性は認知症により要介護状態。デイサービスへ通いつつ在宅介護を受けていますが、家族からは色んなことを忘れて、何もできなくなってしまったと思われていました。しかし、会話の中からロックが大好きで、ギターを20本持っていたことが分かりました。が、認知症を理由にそのギターは処分されてしまいました。
軍司さんは、趣味でギターも弾いており、その和製リッチーこと高齢男性と、「僕のギター2本持ち込んでベースとドラムも連れて行ったのでリッチーに専念してもらいながらセッションしました」とその場の様子を明かしています。
この様子に感激した和製リッチーの奥様、また新しいギターを買ってプレゼントする事に。今後、ケアプランの長期目標が「あのハコで定期的に演る」が目標となりそうです。ちなみに、「あのハコ」というのは「常連だったライブハウス」の意味だそう。常連でロックギター鳴らしていた世代、想像するとカッコいいものがあります。
最高にクールでロックな「介護」に、「一緒にセッションしたい」という声や「享年98歳の祖父、LUNA SEAやBUCK-TICK知ってて、Xが何故X JAPANになったかまで説明出来る人でした」「ご飯は介助で食べてる方がピアノの演奏ができたり、針を持たせたらミシンより正確な仕事をする98歳という方もいました」などなど、介護の現場からも家族からも、高齢者の特技や趣味が輝いていたといった内容のツイートが多く寄せられています。
https://twitter.com/s1_gunji/status/1161934887261110272
■ 認知症の記憶の引き出しは意外なところで開く
認知症になると、さっき食べたものも思い出せない、服を着るにもズボンを袖に通すなど、できなくなってしまうことを挙げてしまうとキリがないほどになってしまいます。しかし、そうした「自分でも不可解なできなくなっていく事」に対して、強い不安を覚えるものです。
家族や介助者は、その「できない」場面、部分ばかりを見てしまいがち。「まだ覚えている・できる」部分に本当はクローズアップする方が、実は介護が少し楽しくなります。そのきっかけとなるのは、対話。
テレビでもラジオでも、何かの本でも隣の人の会話でも、とにかくきっかけはどこにでも転がっているもの。ただそういうのを一緒に見たり聞いたりするだけでなく、「そういえば昔何が趣味だった?好きだった事って何だった?」ときっかけから話を引き出すことで、その人の意外な一面を見つけることができます。
先述の和製リッチーも、そんな対話がなければデイでのセッションもかなうことはなかったでしょう。気持ちに余裕がないとなかなか難しい事ではあるのですが、何気ない雑談こそが、会話ができる認知症の人のケアに大きく役立つことが往々にしてあるものです。
■ 共通の楽しみから引き出す会話と、そこにつなげるケア
筆者は、5年ほど前まで、約8年間デイサービス(正確にはリハビリができるデイケア)にて看護師として勤務していました。午後の時間にレクレーションを行うデイも多いかと思いますが、筆者が勤務していたところも同様にレクを行っていました。介護職員だけでは手が回らないので、筆者も介護職員とともに運動系や頭脳系など、様々なレクを考えては参加していました。その中で共通して楽しめることのひとつに、「歌」があったのです。
童謡や唱歌は、ぶっちゃけノリが悪かったのですが、当時の80代前後の人たちが良く知っている昭和歌謡をみんなで歌う会を、歌詞カードを配って開催してみたところ、認知症があってもなくても、「あの頃は終戦直後で……」「私が女工をしていたころは……」「GS(グループサウンズ)全盛期で俺もギター片手に……」「石原裕次郎のコピーやってた」と、1曲終わるたびに話に花が咲くこともたびたび。筆者も馴染みのある曲から幾つか歌えるように練習して、一緒に歌ってみたところとても喜ばれた記憶があります。
そんな会話の中から、得意なこと、やれることをを拾っていき、「○○さん、これお願いしてもいい?」と雑用を頼むと、喜んでやってくれるのです。曰く、「こんな自分でもまだ役に立てるのならいくらでも」。
できないことに主眼を置かれていることは、介護されている本人もよく理解していて、「自分は老いぼれたお荷物だ」と感じている人は多くいました。しかし、その中でも「まだやれることがある」という手ごたえは、認知症があっても感じることができ、自己否定に陥りがちな介護される人の気持ちに肯定感を生み出す事もできます。
■ 介護のプロができること
「介護されるようになって辛い、悲しい」という気持ちを、「介護されるようにはなったけど、まだこれならできる」に転換できるようにするのは、介護者の大きな役目の一つかもしれません。その人らしい老後を送って欲しい、家族ならそう思う人も少なくないでしょう。だから、家族だけではなく、介護のプロの力を借りて、最期までその人らしさを失わないよう、ケアプランを立てていくことは大事なのです。家族だけだと必ず煮詰まります。たとえ認知症を患っている人の子どもが介護職や医療職でも、家族が相手だと感情が近すぎるゆえに煮詰まってしまうのです。
だから、第三者を通すことは必要不可欠。家族が知らなかったその人の意外な一面を見出すのは往々にして第三者である介護のプロたちです。今、その介護のプロは低賃金にあえぎ、一家を養えるほどの給料が出ないところも多いところもあるがゆえに、常に人手不足に陥っています。筆者も、デイにいた時にもっとゆっくり話を聞きたい、と思っても他の業務に足を取られてなかなか思うようにいかなかったこともありました。
今後、介護のプロをどのように増やしていくかは行政にかかっていると思います。ただ、介護される側と家族、そしてケアマネージャーを含むその地域の草の根的なつながりは、「地域で介護」の土台を育んでいくと思います。かつて、「地域で子育て」をしていたように。
<記事化協力>
軍司 大輔さん(@s1_gunji)
(梓川みいな/正看護師)